
こんにちは。
元美術教師のうさぎ先生です。
今回の記事では、わたしが教員だった時に実際に美術の授業の自習で活用していたDVD映像作品について取り上げていきます。
- 自習時間の活用方法が分からない
- 学校現場における著作権の扱いについて気になる
- 中学の集団授業に適した映像作品について知りたい
こんな人におすすめの記事です。ぜひ最後までご覧くださいね。
自習授業の扱いは難しい
実技教科ならではの悩み…授業回数の統一
曜日によって授業回数が違う場合、少ない曜日に合わせて他の教科に授業をあげたり、他の教科の授業をもらったりすることで、なるべく同じ授業回数に調整するのが基本のやり方です。
しかし祝日の関係などでどうしても授業回数が合わなかったり、外せない出張が入ったりすることもありますよね。
美術のように実技を伴う授業においては特に、授業回数の多さがそのまま作品の評価に影響しかねないですし、特定のクラスだけが作品を進めると損だとか得だとかいう意見が出てきてしまうので、《今の単元とは関係ない別の何か》をさせる必要が出てきます。
そこでわたしが選んでいた方法が、映像作品の鑑賞です。
自習で映像作品の鑑賞をする意味
「ビデオを見せるだけじゃん」と思われないように、美術の授業の時間をわざわざ使って見せていることの意味を説明できるものを選んでいました。
しっかりとプリントを作って、お話の感想ではなく、美的ポイントを見つけやすいように誘導することも必要です。貴重な授業時間ですからね。

単に時間潰し用っていうふうに
捉える先生も中にはいますが、
それはもったいない!と思うのです
でも実はこれは自分自身を苦しめている部分もあって、ただ見せて時間潰して終わりにできなかった分、映像選びが大変でした……。
そんな中でせっかく「これは授業で使える!」という映像作品を複数見つけたので、このブログでぜひ共有したい!現役の先生の役に立ちたい!と思ったんですよね。
自習用の映像選びの4つのポイント(中学校)
ポイントを4項目に分けてみました。
- 時間は90分程度、もしくは45分程度におさまるもの
- 思春期の女子が見て動揺しないもの(女子校勤務だったので)
- DVDが販売されているもの
- 美術分野の中で言うとここが特徴的だよ、と説明ができるもの
1つずつ詳細を見ていきますね。
①時間は90分程度、もしくは45分程度におさまるもの
勤務校では50分授業が連続2コマだったので、どんなに長くても100分までしか流せなかったのです。
2コマ連続のうち1コマだけ他の教科にもらってもらえる場合もあったので、そういう場合は50分までになりますね。
翌週に続きを見せれば?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、今回はあくまでも自習の調整用なので、一度で完結することが大前提なのです。
この制約はどうしようもないので、一番選択肢が狭まる要素です。
②思春期の女子が見て動揺しないもの
端的に言えば、エロくない必要があります。
ちゅっとキスシーンぐらいなら「きゃー!」で済むのですが、洋画だといろいろと刺激的な破廉恥シーンが多くて困っちゃうんですよね……。
おうちで「授業でこんなもの見せられた」と話すかもしれないので、暴力的なセリフや場面が出てくる作品もなるべく避けていました。
児童虐待やDVなどの描写がある作品も、たとえそれを肯定的に描いているわけではないとしても、わたしは学校の授業として見せるものではないと考えて避けるようにしていました。(でも意外とあって、選ぶ時に気を付けていました…)
中学生という多感な年頃ですし、トラウマを抱えている子もいますからね。
③DVDが販売されているもの
わたしのパソコンではBlu-rayを再生することが出来なかったので、DVDが販売されているものを選んでいました。
最近はBlu-rayとDVDの二枚組の商品も多いようですが、再生する時に間違えないようにしてくださいね。
自習監督を他の先生に依頼する場合は、当日の再生機器についても要確認です。
④美術分野の中で言うとここが特徴的だよ、と説明ができるもの
今この子たちに見せてどれだけ意味があるか?その特徴は説得材料になり得るか?というところに気を付けて選んでいました。
「世界最古の長編カラーアニメーション映画だよ」とか「背景画っていうジャンルがあるんだよ」など、事前に考えたり調べたりしておけば何かしら説明はできるので、準備が大切です。
単に「かわいいよ♪」だけでは、さすがに見せられませんからね。
学校におけるDVDの著作権について
授業中の上映は認められている
自分自身が学生の頃も授業中にDVDを鑑賞した記憶はあったのですが、いざ着任するとDVD見せていいのかな?と不安になり、新人なりに調べました。
著作権については第38条から、学校の授業での上映というのは特別に認めてもらえているのだと判断しています。
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRICより
授業で見せるために担任の先生が教育番組などを録画することは、授業の過程における複製(35条1項)に該当しますので、著作権者の許可なく行うことができます。また、授業で生徒に上映して見せることは、非営利無料の上映(38条1項)条に該当しますので、これも著作権者の許可なく行えます。
学校編 | 著作権Q&A | ACCSより
ただし、動画投稿サイトへのアップロードはこれらの規定に該当しませんので、公衆送信権の許可が必要ですから、著作権者の許可なく行うことはできません。
詳細著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
詳細学校編 | 著作権Q&A | ACCS
一方、文化祭での上映など不特定多数の人が関わる行事だと、たとえ学校で実施だとしてもまた違う扱いだという見解もあるようですね。
あくまでも認められているのは授業中のみ、ということです。
レンタルDVDだとダメ?
わたしはたまたま行動圏内にレンタルショップがなかったこともあり購入したDVDで見せていましたが、レンタルDVDだと違う扱いだという見解もあるようです。
詳細ビデオコピライトFAQ|一般社団法人日本映像ソフト協会
ちなみに第35条で学校について触れられていますが、わたしは《ディスクの複製》をする必要はなかったので……どうなんだろう。
ここは商品によるのかな?と思っています。コピーガードがかかってたりしますよね。
もしも複製を希望する場合は、発売元へのお問い合わせをおすすめします。
わたしは法律に関して全く明るくないので、あくまで私見ということでお願いしますm(_ _)m

それではここから、具体的に
作品についてご紹介しますね!
『白雪姫』本編83分
- 本編83分
- ラストの「ちゅっ」ぐらいなので問題ないと思いますが、上級生は白けるというか冷めてみてしまう場合もあるので、中1におすすめです。
- 多様な形態で発売されています。
- 1937年公開の世界最古の長編カラーアニメーション映画ということ、手塚治虫さんが何度も映画館に足を運んだこと、実際の俳優さんがモデルになって描き起こされたことなどを紹介しました。
ディズニー作品ということでメジャーなものではありますが、意外と「映画はちゃんと見たことない!」っていう生徒も多かったです。
90年近く前に作られたとは思えないような水面の表現など、文字通り色褪せない魅力が詰まった作品になっています。
名作だけあってDVD・Blu-rayなどいろいろなバージョンが発売されていますので、学校で再生可能なディスクを選択してくださいね。
『ナイトメア・ビフォア・クリスマス』本編76分
- 本編76分
- ホラー表現が怖いという子もいるので、前振りをしてから見せていました。
学校行事が多くて授業時間数を揃えるのが大変な2学期に見せると、ハロウィンやクリスマスの時期とも近くてちょうどよかったです。 - 多様な形態で発売されています。
わたしが持っているコレクターズ・エディションは短編が2つとメイキング映像も入っていたので、時間に余裕がある時にはメイキング(英語ですが)も少し見せていました。 - ニャッキ!やピングーを例に、ストップモーションアニメの仕組みを解説してから鑑賞を始めることをおすすめします。
「ここはどうやって撮影しているんだろう?」「あっいま針金見えたんじゃない?」と撮影方法に興味を持って見る生徒が多くいました。
こちらもディズニー作品ですが、『白雪姫』とはかなり毛色が異なります。
ストップモーションアニメの仕組みがわかると見え方が変わって面白いので、ぜひ撮影方法の解説とあわせて活用してほしい作品です。
メイキング映像などが収録されていない本編のみDVDであればAmazonで1000円を切ることもあるので、用意しやすい作品でもあります。
ちなみによく勘違いされますが、この作品の監督はヘンリー・セリックさんです。ティム・バートンさんは原案やキャラクター設定の担当ですよ。
『時をかける少女』本編98分
- 本編98分なのでギリギリです。
- 甘酸っぱいラブストーリーです。
千昭派か功介派かで話題は持ちきり、黄色い声援がすごいです。
ちょっと反抗期が入ってきた中2におすすめです。 - 多様な形態で発売されています。実写版と間違えないでくださいね。
- 美術監督の山本二三さんは『もののけ姫』や『天空の城ラピュタ』も手がけていることを紹介し、背景画家という存在を知る、人物と背景は別々に描いているというアニメーションの仕組みを知るきっかけにしてました。
細田守監督作品はポピュラーなアニメ映画として浸透しているかと思うのですが、最近の作品だと少し激しい描写やトラウマに触れかねない演出もあるので、あらかじめ先生がご覧になった方がいいと思います;;
そういう意味でも、さわやかな青春を描いた「時かけ」はおすすめです!
背景画家の解説については山本二三さんと同時に男鹿和雄さん(トトロ)や井上直久さん(猫の恩返し)も紹介すると、より興味を引くことが出来ますよ。
『セロ弾きのゴーシュ』本編63分
- 本編63分
- 自立や将来について考えるストーリーなので、中3におすすめです。
- DVDとBlu-ray、それぞれ1種類の発売みたいです。ジブリならではの『徳間アニメ絵本』もあります。
- 音楽と映像が融合する面白さが特徴的だと事前に伝えました。
また、高畑勲さんは現実的なストーリー、宮崎駿さんはファンタジーなストーリーが多いという特徴を紹介することで、今まで何気なく触れ合っていたジブリが監督によって毛色が違うことに気付かせる機会になりました。(そもそもジブリ=宮崎さんだと思っている生徒が多かったです)
前置きとして、高畑さんのメッセージにも触れるようにしていました。
自立に向かって苦闘している中高生や青年達にもぜひ観てもらいたい
『映画を作りながら考えたこと 1955〜1991』徳間書店
本編63分ということで2コマ授業だと少し余裕があるので、鑑賞の前後に高畑さんの紹介をしたり、「虎狩りのシーン」を2回見せたりと、授業時間の融通が効く作品でした。
漫画やアニメの歴史に詳しい先生から、おすすすめされた作品でもあります。
ただ、現代の子どもからすると少し表現が地味に思えてしまうかもしれないので、適宜先生の方で派手さやコントラストの強い光の表現だけがよさなのではないという声かけをすると効果的ですよ。
『ディズニーショートムービーコレクション』(短編集)
- 短編集で、12作品で80分です。
- 1コマ(50分)だけ自習というときに「3作品×2回」見せていました。
「1作品見せる→感想タイム」を3作品分くりかえして、そのあと「連続して3作品」でちょうどいいぐらいです。 - DVDとBlu-rayが両方入った、ダブルディスクです。
- アカデミー賞に短編アニメ部門があることも、ディズニー作品に短編作品があることも、意外と知らない生徒が多いのでこの機会に紹介していました。
よく見せていたのは『ロレンゾ』→『紙ひこうき』→『ラプンツェルのウェディング』の順に3作品です。前の2つはセリフがほとんどなく、音楽と映像の融合という視点で選択。ラプンツェルは地面と空を行ったり来たりするカメラワークに注目してねと伝えて見せていました。
長時間の集中が難しい生徒もいますし、なにかと調整が効く短編集は使い勝手がよくておすすめです!
「健康診断で短縮授業になる日に1本だけ見せる」「避難訓練の後の微妙な残り時間に見せる」という使い方も出来て、助かっていました。
『びじゅチューン!』(短編集)
- 短編集で、うた・かいせつ・カラオケ・特典をあわせて80分です。
- 日本美術や西洋美術に関する鑑賞の授業の中に組み込んで見せていました。1作品につき5分ほどなので、1コマ(50分)だけ自習というときにも活用できると思います。
- DVDのみ、2023年現在は1〜7巻まで発売されています。
- 歌そのものの面白さはもちろんのこと、“美術作品からさらに作品が生まれる”という面白さについて触れて紹介するようにしていました。
ダントツ人気だったのは『鳥獣戯画ジム』です。
『びじゅチューン!』シリーズは曲が短時間でキャッチーで印象に残るのがいい!ということで、よく活用させてもらっていました。
元々はEテレの番組なので幼い子ども向けだと思われるかもしれませんが、中学生も十分楽しめますよ。
実は社会科の授業でも『風神雷神図屏風デート』などを見せている先生がいらっしゃいました。
とりあえず1つ持っておけば、生徒の様子や学年に合わせて適宜作品を選べるっていうのも短編集のいいところですよね。
ちなみに井上涼さんも、上に出てきた細田守さんも、わたしの大学の先輩にあたります。
美大出身者がこういった映像作品制作に関わっていることを、ちょっとしたキャリア教育として紹介したこともありました。
見せたかったけど、いろいろな都合で選べなかった作品
『パコと魔法の絵本』
『下妻物語』『告白』などで知られる中島哲也監督作品です。
病院を舞台としたとってもかわいい成長物語で、アニメや舞台の要素が使われた映像も魅力的で個人的には大好きな実写作品なのですが……。
まず本編が105分と長すぎるいうことと、暴力など一部過激なシーン・発言があるので断念しました。
『パプリカ』
すごく好きなアニメーション作品なのですが、悪夢のシーンが怖すぎるのと、少し破廉恥なのと、全体的に中学生には設定の理解などが難しいお話かなと思い断念しました。
今敏監督作品は他にも『パーフェクトブルー』『東京ゴッドファーザーズ』など個人的にはおすすめしたいのですが、いわゆる万人受けとは少し違っているんですよね。テーマが重たいものも多いです。
高校生が相手なら見せてもいいかなと思います。本編90分です。
『アリス』
物語のベースはよく知られた『不思議の国のアリス』なのですが、全体的にちょっとホラーというか、アニメーションと実写をミックスした演出には独特の不気味さがあるんですよね。
それがヤン・シュヴァンクマイエル監督作品のよさでもあり好きなところなんですが、大型スクリーンで授業として中学生に見せるには抵抗がありました。
この作品も高校生が相手なら見せてもいいかなと思います。本編84分です。
3つとも、前置きをした上であれば、生徒に個別におすすめできる作品ではあります♪
おわりに
今回は、美術の授業の自習に使える映像作品をご紹介しました。
急な出張や体調不良で「映像を前もってじっくり見る・選定する時間がない!」というときに限って、自習が訪れたりするものです。
映像選びに困っている先生たちにとって、この記事が少しでも参考になったら嬉しいです。
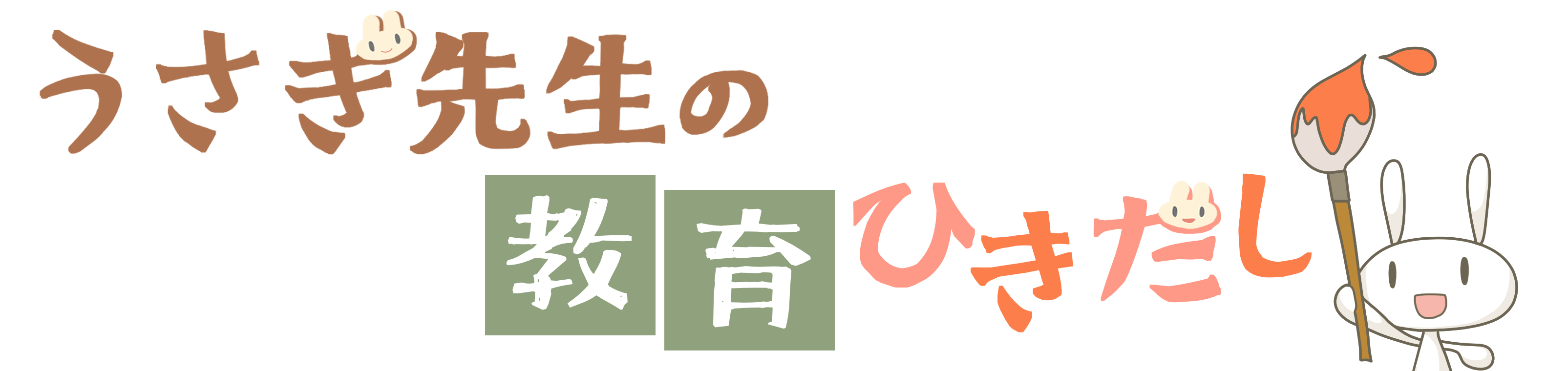
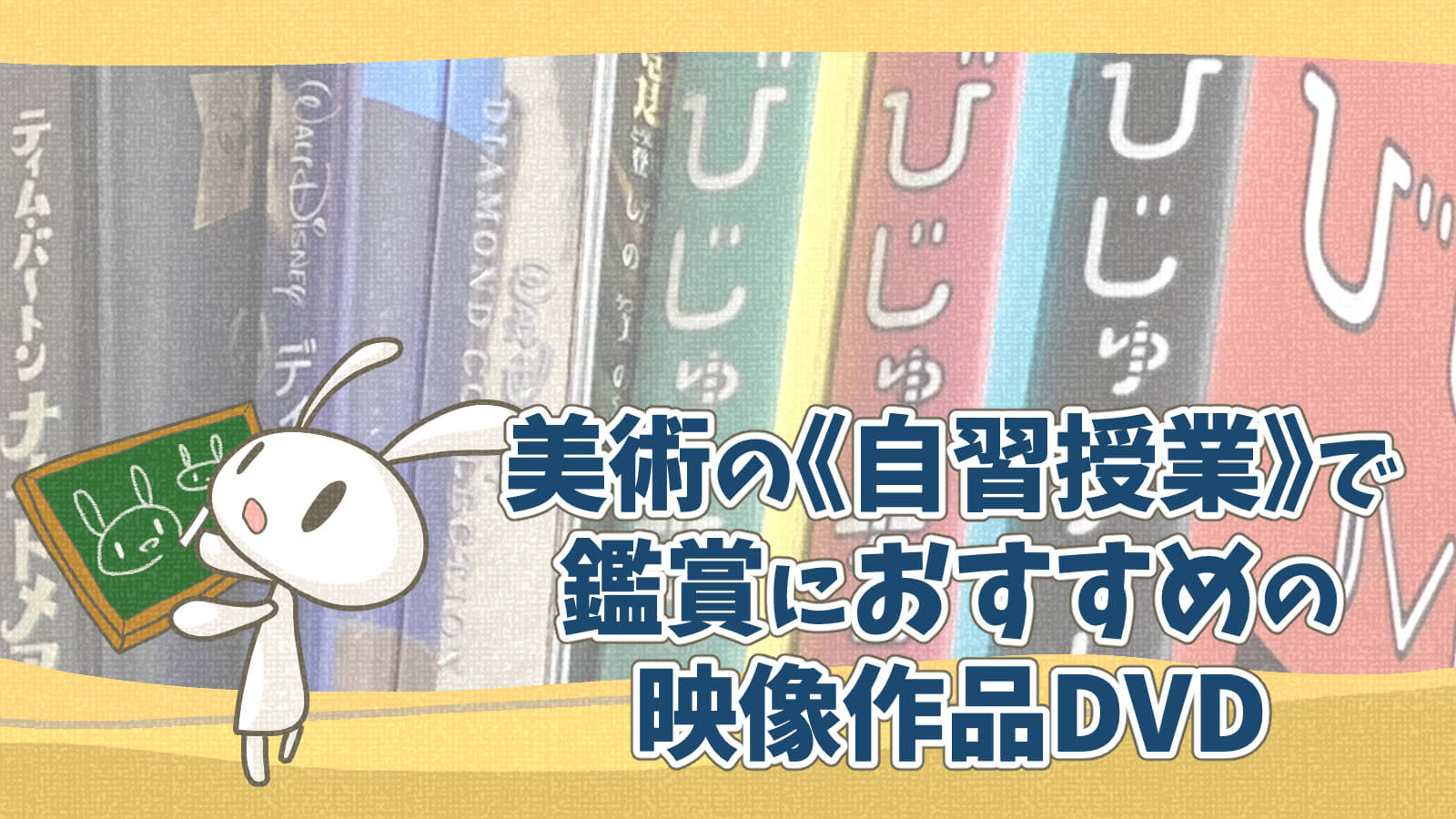
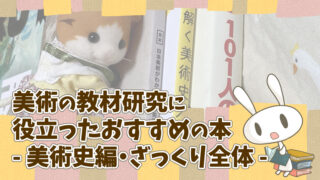
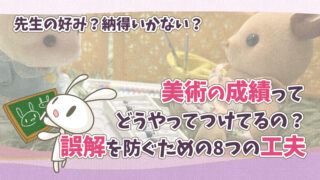
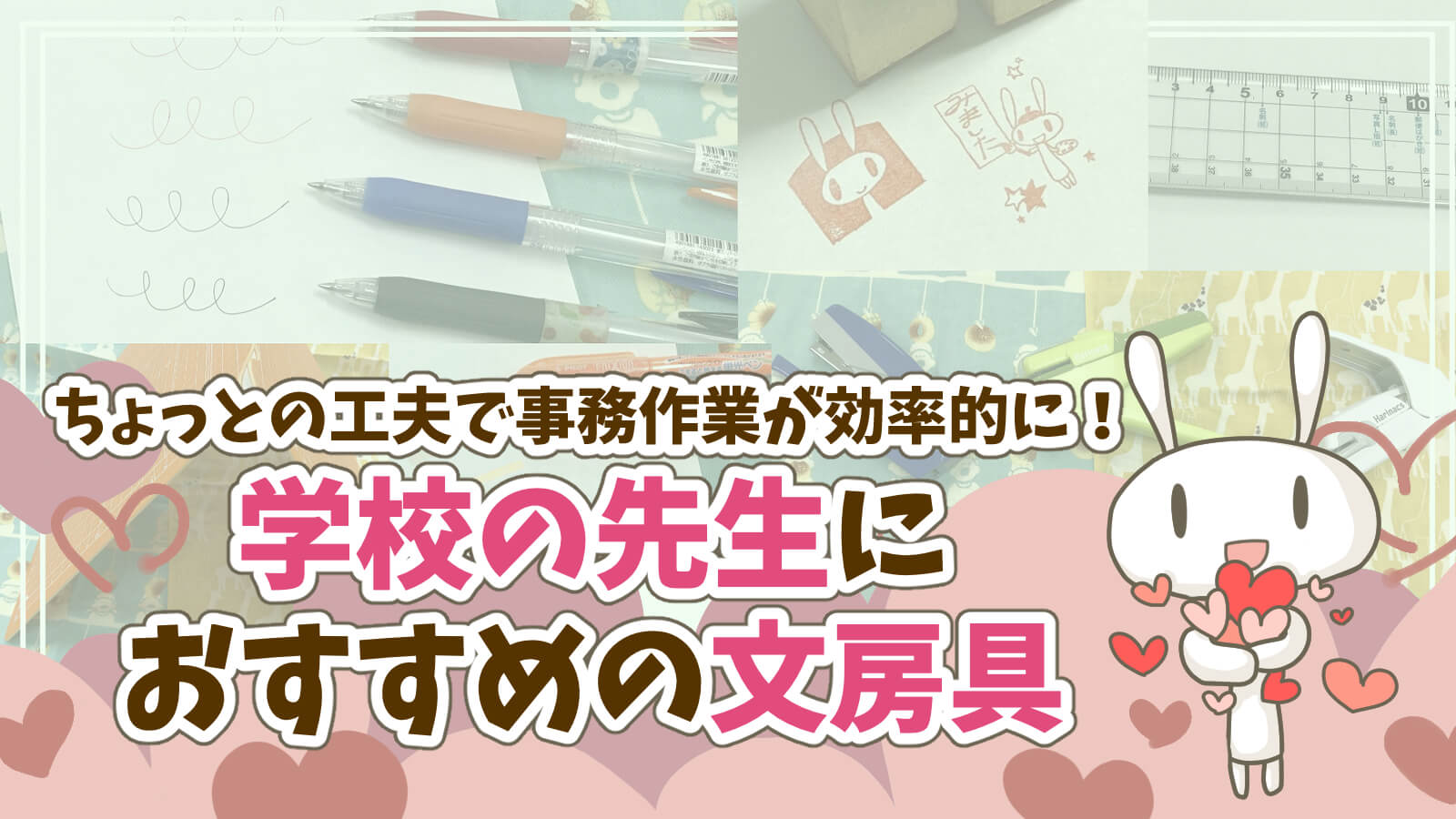

コメント