
こんにちは。
元美術教師のうさぎ先生です。
前回は「清算と精算」や「調度と丁度」を例に漢字の使い分け・誤りについて気になるところを一つの考え方として書きました。
今回は、もう一つの気になるワード「ふう」と「風」について、改めて調べてみることにしてみました。
漢字の使い方というよりは、ひらがなにするか漢字にするか?という話ですね。

プリント作りや板書の際に
よく出てくる言葉なので
気になっていたんですよね
ふう?風?
わたしの認識ではこんな使い分けです。
「こんなふうにやってね!」
ならふう(ひらがな)
「キティちゃん風の色合いです!」
なら風(漢字)
わたしは国語の先生ではないので詳しく何かを知っているわけではありませんが、自身が授業をするときや学級通信を作るときにはいろいろと気にした部分なんですよね。
「ほとんど」「ようやく」なども、ひらがなで表記するようにしていました。
と言っても、自分自身が中高生の頃は中二病だったので(笑)、ついつい「殆ど」「漸く」などと漢字に出来る限りは漢字で表記していたのです。
それが大学生ぐらいのとある時に、「本に出てくる場合、ほとんどひらがなだ!読みやすい!」と気付いたんですよね。
でも、文法的に間違っているのか?というと、そこは曖昧でよく分からなかったんです。
文字をひらくという考え方
正解も間違いもない…けれど
文字校正に関するこんな記事を見つけました。
参考まだ「文字校正」で消耗してるの? LIGブログの表記ルールについて整理してみた【2018年版】 | 株式会社LIG(リグ)|DX支援・システム開発・Web制作
文字をひらく、という考え方があるそうです。
- 「ひらく(開く)」=「ひらがなにする」
- 「閉じる」=「漢字にする」
ひらがなと比べると漢字は情報量が多いので、それだけ読むのにも時間がかかってしまうんですね。読み手にとって負担が大きいとも言えます。
「風」でも「ふう」でも問題はないけれど、読み手のことを考えると「ふう」のほうがスラスラと読みやすい場合がある、ということでよさそうです。
こちらの別の記事でも、読みやすさを考えたときには使い分ける必要があると言える、ということが書かれていました。
参考漢字を多用しない|SEI STREET
「~のはず」「~ということ」や「なるほど」「できる」なども、ひらがなのほうが読みやすいと例に挙げられています。
読みやすくするための工夫
今度はこの《文字をひらく》という言葉について調べてみると、文法の視点からとても詳しく解説されている、こんな記事に出会いました。
参考【校正】ひらく漢字の決定版!常用漢字表(H22改正)ほか | ことばのよろず屋
参考ひらがなで書く方がスマートな漢字50選|コピーライター|中村 和夫
どうやらひらくルールは完全に決まっているというものでもないようです。
記事全体・メディア全体での統一が雰囲気づくりには大切とのことで、文章のお仕事をしているかたにとってはクライアントごとに書き方を変えるなどの工夫や苦労があるようですね。
そして同一コンテンツ内でうっかり表記が変わってしまうことを《表記揺れ》と呼び、「表記揺れを防ぐ」のように使うそうです。
複数人のライターがいるサイトなどでは、表記揺れに注意が必要になりますね。
学校現場は表記揺れだらけ?
文字をひらくリストがほしかった
わたしの「ふうと風」に対する違和感は、ある意味では伝える側・表現者としてのセンサーが正しく働いたんだなぁと嬉しく思いましたが、教員時代にはこの違和感に共感されないことも多かったんですよね…。
同じ学校が出しているプリントや広報パンフレットなのに表記揺れがあるっていうのはわたしはけっこう気になるタイプだったのです。
実際に、「お姉ちゃんのクラスと、三者面談の用紙の仕様が違いすぎて見づらい」なんて声が保護者さんから上がったこともありました。
でも何十人と先生が働いている場では統一しようとするのはなかなか大変だったというのもまた事実なので、正直なところ表記揺れだらけでした><
生徒のレポートを添削する際にも判断に迷うことが多かったので、△△学校版・ひらく漢字リストみたいなものがあったら、もう少し業務がスムーズに進んだだろうなぁ…なんて思うこともありました。

「各自先生に任せます」だと
一見楽なように見えて…
判断するっていう手間が増えて
けっこう面倒でした;;
教育大系だと体裁や漢字の使用に厳しい?
ちなみに指導案についても、わたしの元勤務校(私学)ではどんなスタイルでも問題ありませんでしたが、教育大付属系の学校だとかなりしっかりと体裁や使用可能漢字が決まっている場合が多いそうです。
一部の教育大だと教員免許取得のための授業では常用漢字以外は使わないようにという指導を受けるらしいので、文字をひらくことについても指導を受けるのかもしれませんね。
おわりに
今回は「ふうと風」を例に、文字をひらくという考え方について調べてみました。
「風」でも「ふう」でも問題はないけれど、読み手のことを考えると文字をひらいて「ふう」としたほうがスラスラと読みやすい場合がある
余談ですが…最近では「(笑)」が「w」になって、さらには「草」と、笑うことの表現が大きく変化してきました。
文法的にはすべて誤りだとしても意味としては通じることがありますから、言葉として完全な誤りとは言えない気がします。
《文字をひらく》こととはまた別ですが、言葉って不思議で面白いですね。
ただ、TPOというか…場の誤りとでも言うのでしょうか。
極端な例ですが、三者面談の保護者案内や学級通信に「草」はまず使わないですよね。
でも、生徒とのメモのやりとりや日誌コメントなら「(笑)」ぐらいは使うことがあると思います。
そこは生徒との距離感や親密度に応じて使い分け・判断が必要ということですね。
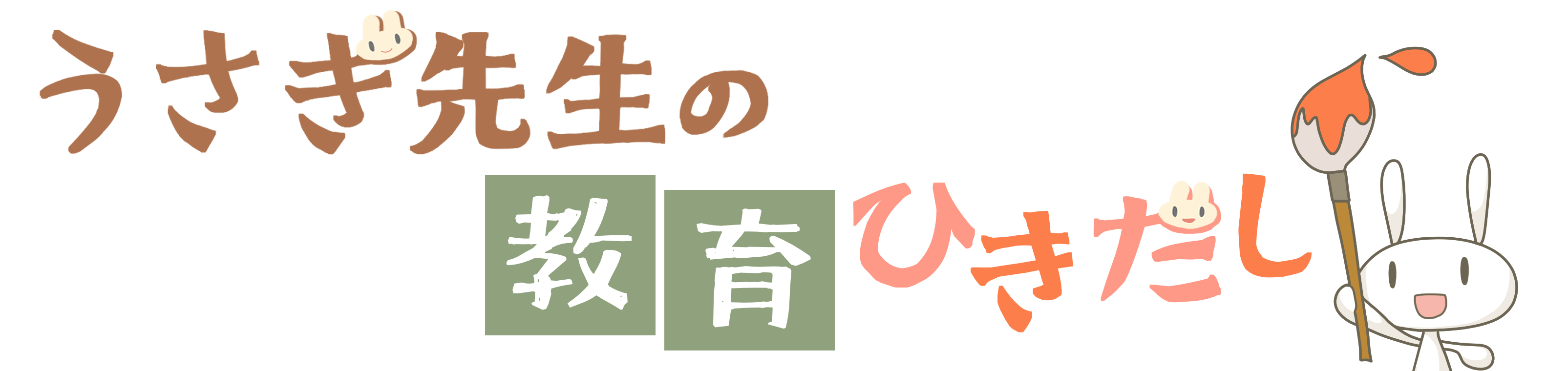
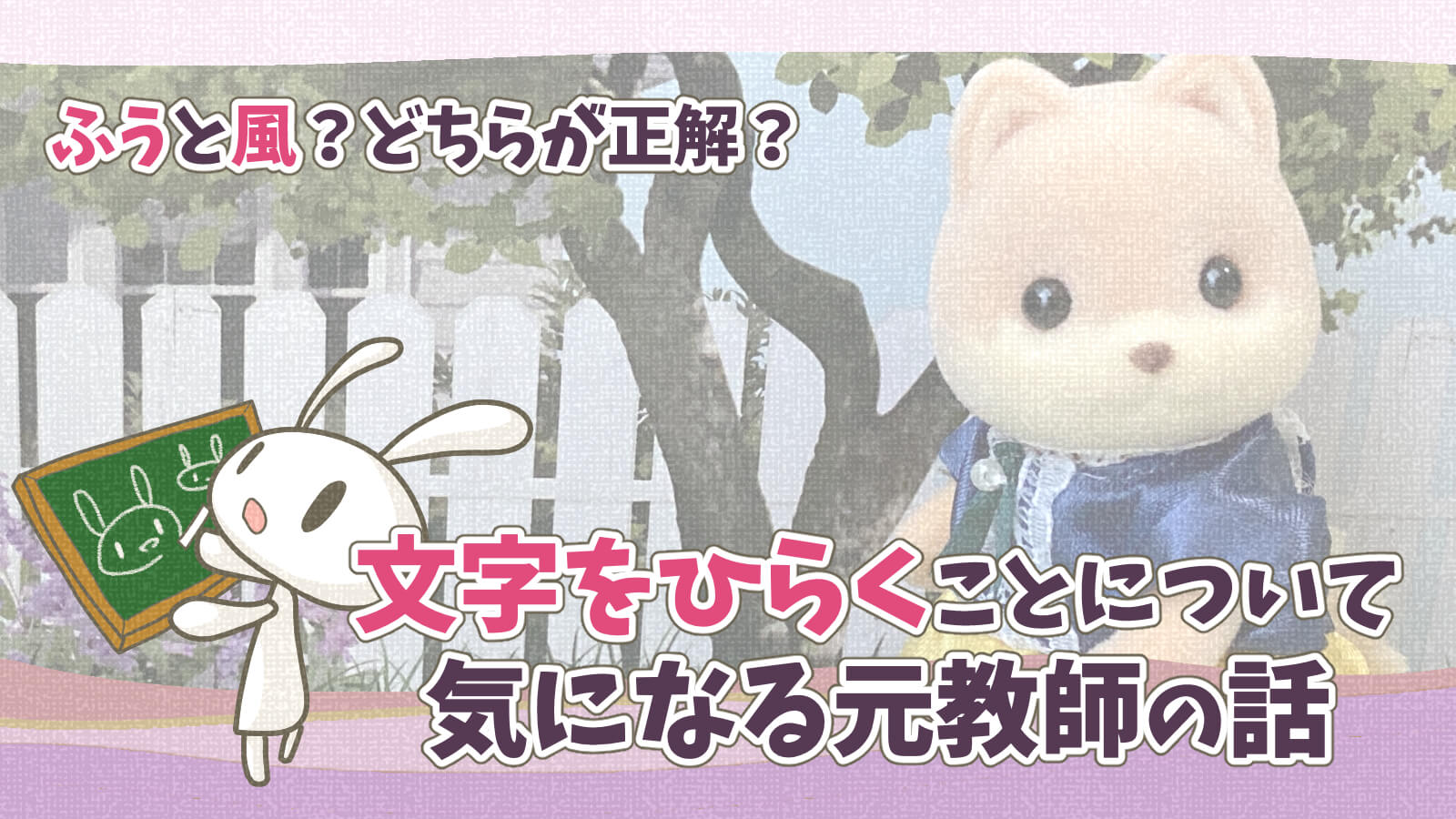


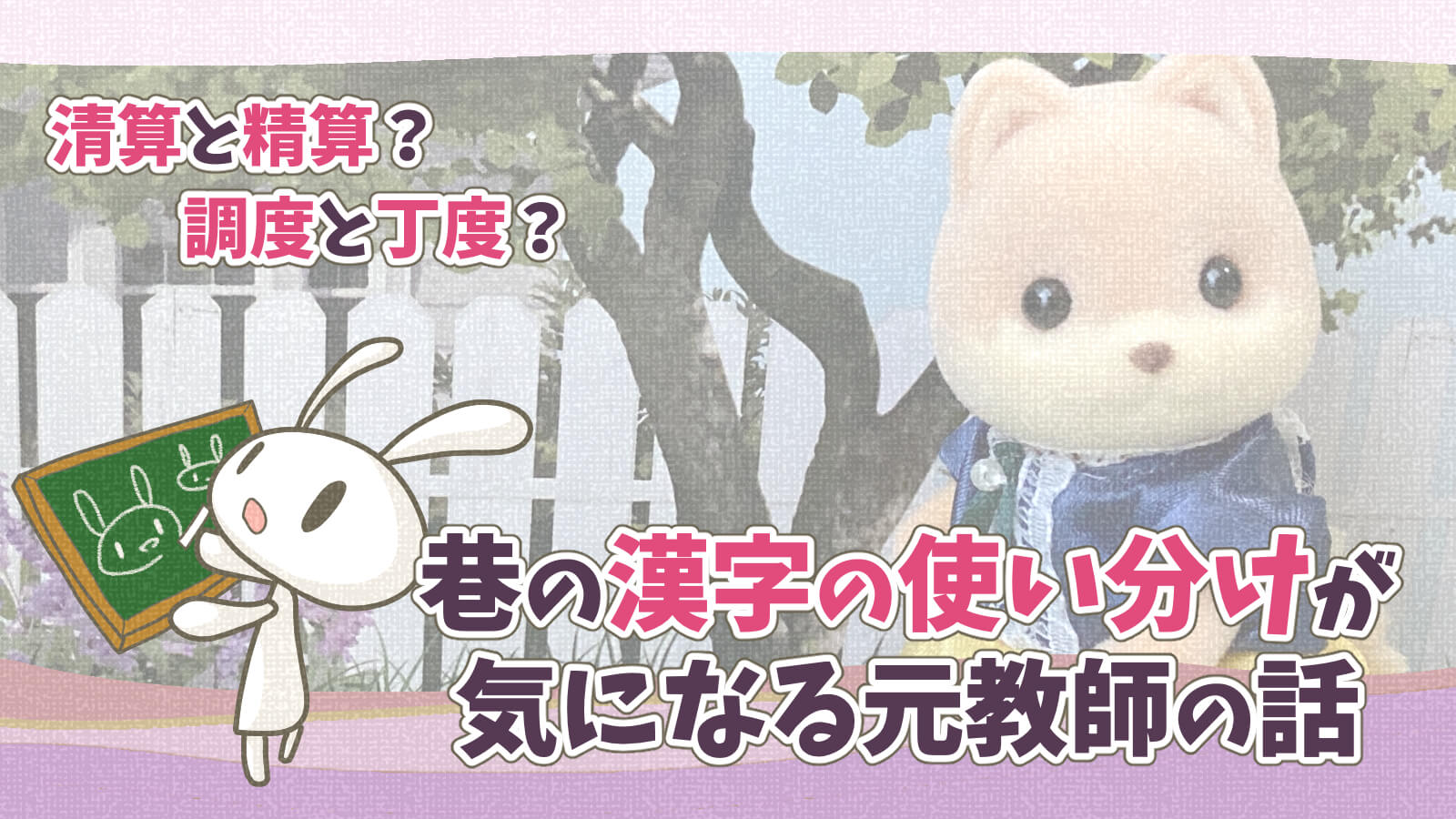

コメント