
こんにちは。
元美術教師のうさぎ先生です。
ある日見かけたアンケート記事に「一番役に立たない教科は美術」という気になる話題がありました。
これって「美術の授業は何のためにあるのか?」とも受け止められると思うのですが、実は教員採用試験の勉強をする中で、美術教師を志す人が必ず触れるテーマなんですよね。
今回の記事では、この美術の授業の目的について考えていこうと思います。
- 一番役に立たない教科は美術だと思う
- 美術の授業が何のためにあるのか分からない
- 副教科の授業は無意味だ
こんなふうに考えている方は、ぜひ最後までご覧くださいね。
大人になって「役に立っていない」と思う教科
発端は、こちらのアンケート記事なんですけど…
はい。1位が美術なんだそうです。
■第1位:美術(20.7%)
多くの科目を抑えての1位は美術。絵画や工作などを学ぶが、一般社会でその知識や技術を使うことはほとんどない。そのようなことが、1位になった理由かも。もちろん、覚えておけば役に立つ場面もあるのだが。
https://sirabee.com/2020/05/09/20162300201/
ちなみに2位は理科、3位は数学でした。
実際のところ、美術の授業が嫌いだった・美術の先生が嫌いだったという経験を持つ人は少なくないみたいなんですよね。
以前別の記事の時にも書きましたが、美術の先生は好みで成績をつけているとか、頭が悪いとか、そういう印象を持つ人がけっこういらっしゃるのだとか;;
実際そのような固定観念の目で見られると辛いところがありまして、先生を辞めたいと感じた理由の一つにもなりました。
もちろんそんな先生ばかりではないはずですし相性の問題もあるのですが、現実としては「“そう思わせてしまう授業”をやっている美術の先生が一定数いる」ってことなんだと思うんですよね。
その辺りを紐解いてみたいなというところもありまして、今回は改めて、美術の授業の目的についてわたしなりに考えてみたいと思います。

絶対的な正解がある類のものでは
ありませんので…
あくまでもうさぎ先生なりの
一つの見方ということで
参考としてご覧くださいね♪
美術の授業は「生徒が持つ自己表現の可能性を狭めないため」にある!
結論から先に言ってしまうと、「美術の授業はなんのためにあるか」にひとことで回答するなら、わたしなら「生徒自身が持つ美的な自己表現の可能性を狭めないため」と答えます。
少し噛み砕くと、「色や形を使って便利に過ごす力を身につけるため」そして「「美しい」と感じるものと出会って将来を生きやすくするため」ですね。
こう考える理由は、のちほど具体的に解説していきますね。
「美術大好き」にさせるために授業がある、のではない!
大きな誤解です!
まず声を大にして言いたいことは、「美術教師は生徒を“美術大好き人間”にさせるために存在している」というのは大きな誤解であるということです。
「美術の授業は、美術を大好きにさせるためにある」っていう考え方ですね。
教員時代は他人の履歴書を見る機会も多かったのですが、こんな言葉を目にすることがあったのです。
- 私は生徒全員を美術大好きにさせます!
- 私はこんなアンケートをとって、「美術が好きになった」と全員に答えてもらいました!
- 私は自分の大好きな美術のよさを、美術が嫌いな子に分かってもらいたいんです!
いや……怖いですよね?
わたしからしたら、これは強制・押し付けだと思ってしまうんですよね;;
「好き」じゃなきゃ、ダメなのか?
別に嫌いな教科が一つや二つあってもいいですよね。
「生徒全員を美術大好きにさせます」という言葉は、わたしにはどうしても、美術を嫌いだと言う子の気持ちや人生経験を否定している感じがしてならないんです。
無理やりに振り向かせようとしている感じっていうんですかね…。
もちろん結果的に自分の教科を好きになってくれれば嬉しいですし、ドキドキわくわくしてもらいたくて工夫を凝らした授業をしますけれど、まずは以前よりも興味が湧くぐらいが現実的なラインだと思うんですよね。
「絵の具めっちゃ嫌い!」って言って入学してきた子が、混色の仕組みを知って、水入れを倒さないコツを知って、「なんか好きな色できたかも!」って言ってくれたら…
わたしなら、よっしゃー!って心の中で叫びますよ。
成功体験させてあげられた!って、とても嬉しいです。
でも、もし「美術が好きになった?」と聞いたら、その子はきっと今まで通り「嫌い」だと答えると思います。思春期ですしそういうもんですよね笑

心の中に芽生えた小さなワクワクが
生徒の自己表現を狭めないために
すごく大事だと思うんですよね。
「こいつに迎合してたまるか」なんて
タイプの生徒もいるし、聞くのは野暮!
生徒の気持ちに寄り添っていますか?
誤解を恐れずにいうと…
つまり《美術を大好きにさせたい先生》たちっていうのは、生徒の気持ちに寄り添えないタイプの先生なのかな?と感じてしまうってことなんです。
「じゃあ先生は数学好きなんですか?英語も好きなんですか?」と尋ねてみたいですし、「もし好きにさせてみせる!って9教科の先生全員に言われたら、生徒はどう思うと思いますか?」とも聞いてみたいです。

だから美術の先生は、
えこひいきしてるだとか
好みで採点してるだとか
言われがちなんじゃないかな…?
この記事を読んでくださっている方の中に「よい美術の先生と出会えなかった」と感じている方がもしいらっしゃったら、このようなタイプの先生だったのかもしれませんね。
学校の授業は、プロにするための場ではない!
これは他の教科だって同じですが、そもそも中高の美術の授業を受けたからって、全員が画家になるわけではないんですよ。
全員が数学者になるわけでもないし、全員が日本語研究者になるわけでもありませんよね。なんなら大学レベルの集団でさえそうだと思います。
義務教育って多くの生徒たちが「うっすらとそれらの知識を持った上で、自分の得意なことの知識や経験を積み重ねていく」っていう土台のような存在なんです。
同時に、美術はなにも高尚なものではないということも伝えていきたいです。
「有名な絵を見てもなんとも思わないんですけど、美術に向いてませんか?」なんて気にしてしまう生徒もいるのですが、全然気にしなくていいと思います!
美術が関わる分野は多岐にわたりますし、当然好みもありますからね。
美術の授業の役立つところ
わたしは美術の授業が必要な理由として「色や形を使って便利に過ごす力を身につけるため」そして「「美しい」と感じるものと出会って将来を生きやすくするため」を挙げました。
具体的に役立つのはこんな場面だと思っています。
色や形を使って便利に過ごす力が身に付く
ファッション
- 同系色が何なのか分からず、まとまりがない服装に…
- 知らず知らず補色になっていて、目立ちすぎる組み合わせになる…
センスがどうとか才能がどうとかいう人もいますが、多くの場合は色彩の知識である程度解決できます。
たとえばトップスが黄緑でパンツが紫だと、『トイ・ストーリー』のバズのようなはっきりと目立つ組み合わせになります。互いを引き立たせ合う補色関係の色味なんですよね。
色の知識が部活の衣装作りに役立った!という声もありましたし、女子校ならではかもしれませんが、お化粧の色選びに役立つと言われたこともあります。

絵の具を塗るのがうまい子は
アイライナー引くのが得意とか
そういう関連性もあるらしい…
文章やグラフ
総合的な学習の時間などで、グラフを作って発表する場面もよくありますよね。
大人になってもExcelなどで資料作りをする仕事は多いと思いますが、プラスとマイナスでどう色を変えるか?とか、見出しと本文にはどんなフォントを使うか?とか、色やデザインの知識が大活躍します。
たとえば白背景に黄色い文字だったりすると…
ほら、読めないですよね。
学校の壁新聞など、「目立たせるために黄色のペンで見出しを書いたら全然見えなくなってしまった…」という経験がある人も多いと思います。
このような「白い紙に黄色のペンで描くと明度が似ていて見づらいから色を変えよう/縁取りをつけよう」や「この形のポーチは鞄の中で収まりが悪いから使いやすい形状に買い替えよう」といった日常的な経験においても、美術の知識を生かせる場は潜んでいるんですよね。
なにも、粘土を捏ねたり絵の具を塗ったりすることだけが美術、というわけではないのです。

空き箱を収納として再利用とか、
カーテンの色を空間に合うように
選ぶとか、そういったところにも
美術で得た力が生きています!
「美しい」と感じるものと出会って、将来が生きやすくなる
現代風に言えば、「推しがいれば人生楽しい」ってことです。
「美しい」「素敵」と思えるときに嬉しくなることは共通していて、それは自分自身を励ます力になるんですよね。
推す対象は人物でも場所でもなんでもいいのですが、それを「美しい」「素敵」だと感じる気持ちが感性で、「いいなって感じるセンサーの多さ」や「好きなものを見つけられる力」だと思ってください。
美術の授業でいろんな色を見て、形に触れて、作品を見ることで、感性が磨かれていきます。いいなって感じるセンサーが増えていくってことですね。
感性が育たないと好きなものが見つかりにくい状態になって、自分自身を励ます力も弱まっていくんです。
どんな服でもいい、どんな髪型でもいい…
「人生どうでもいい」なんてことになるかも…
逆にいうと自分を励ます力をフル活用している人って、「ネイル変えて気分転換!」「季節が変わったからランチョンマット新しくしたよ!」といった形で美術を役立てているんですよね。

ネイルやランチョンマットは一例で、
これがギターでもプラモデルでも
「好き」ならなんでもいいんです。
自分の感性で選んだものが、
自分の心を助けてくれるんですね!
「この道は選ばない」と思える=役立っている
それにそもそも、わたしは義務教育って《選択肢を広げる時期》だと思っているので、「この活動は好きじゃない」「この行事は面白くなかった」……だから将来の道として選ばないことにしよう。
これだけで十分役に立っている、と思うのです。
たとえば習い事をやめたくなったとします。
「ピアノと水泳の両立は大変。
だから、ピアノをやめます。」
じゃあピアノは役に立たなかったのか?必要なかったのか?というと、それは違いますよね。
楽譜を読めるようになったとかそういった技術面はさておき、どっちをやめようって考えた時に水泳のほうが好きって気付くきっかけになったという意味で役立ったと言えます。

ピアノを習っていなかったら、
水泳のよさに気付くことなく
だらだらと通うことになったかも?
「ゴッホの絵みたけど、よくわからないし、ラッセンのイルカが好き」とおっしゃる芸人さんがいましたが、ラッセンの方が好きって気付くきっかけに、ゴッホを知ることは役に立ったわけです。
そういう意味では言えば、「役に立たなかった授業」を問うというアンケートそのものが、ナンセンスな気がしてきますね。
おわりに
今回は「一番役に立たない教科は美術」という気になる話題をもとに、美術の授業の目的についてわたしなりに考えをまとめてみました。
- 色や形を使って便利に過ごす力を身につけるため
- 「美しい」と感じるものと出会って将来を生きやすくするため
「生徒の気持ちに寄り添って、その子が自分なりの美術との付き合い方を見つけるための手助けができる教師」でありたいと思いながら教壇に立っていましたよ。
もちろん先生によって考え方はさまざまだと思いますが、美術の授業の目的や必要性について知りたい方にとって、この記事が少しでも参考になると嬉しいです。
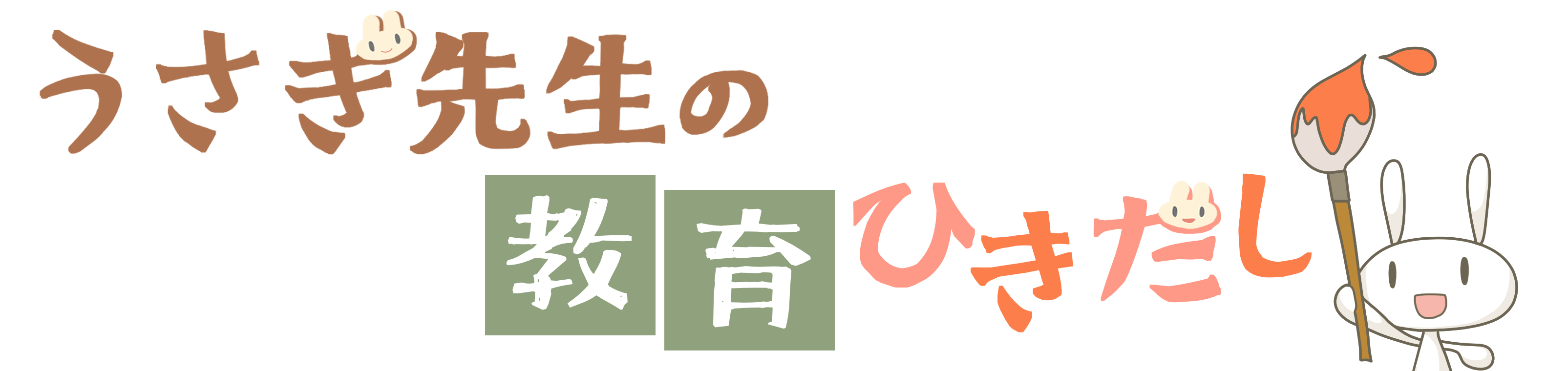
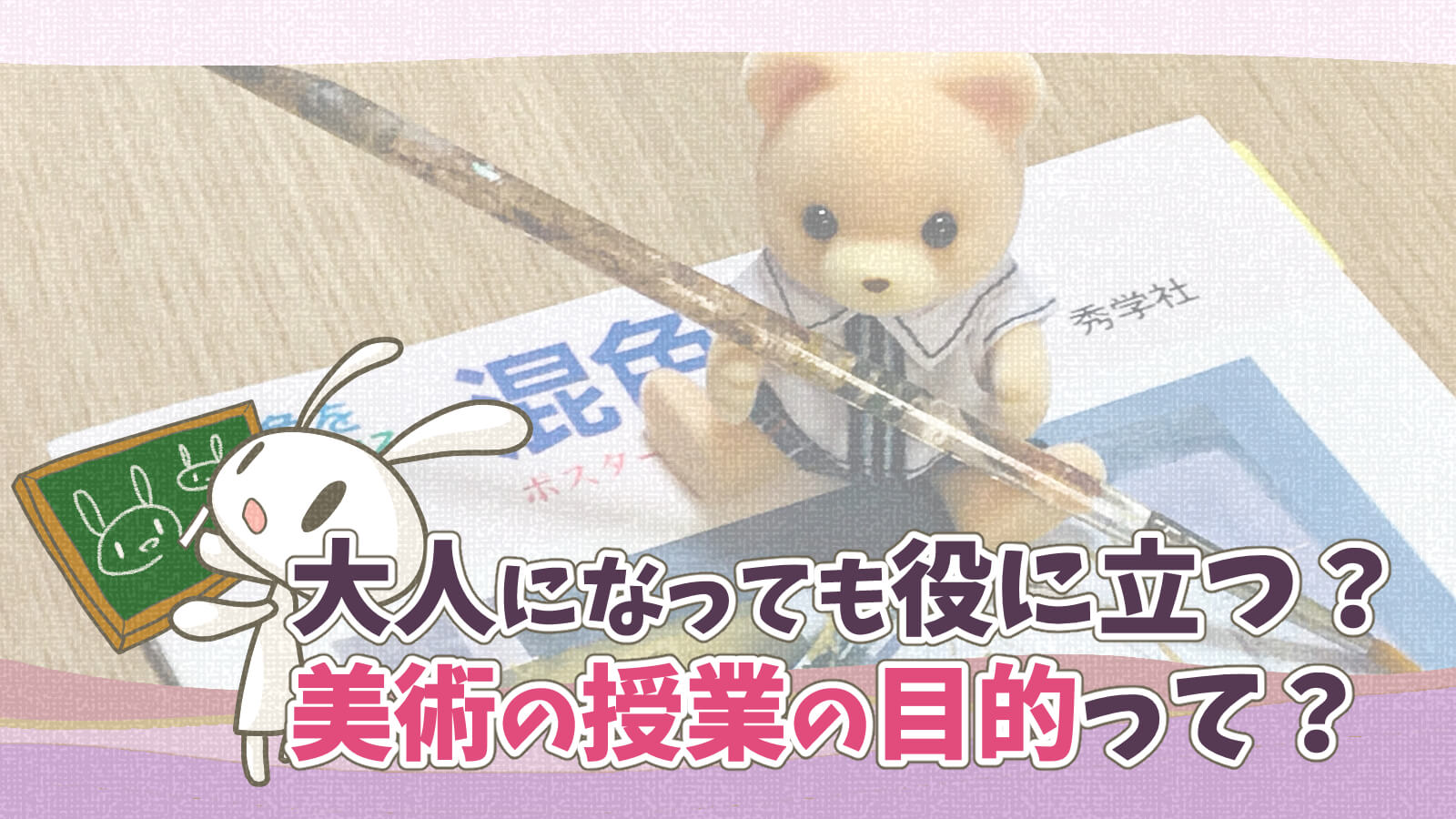
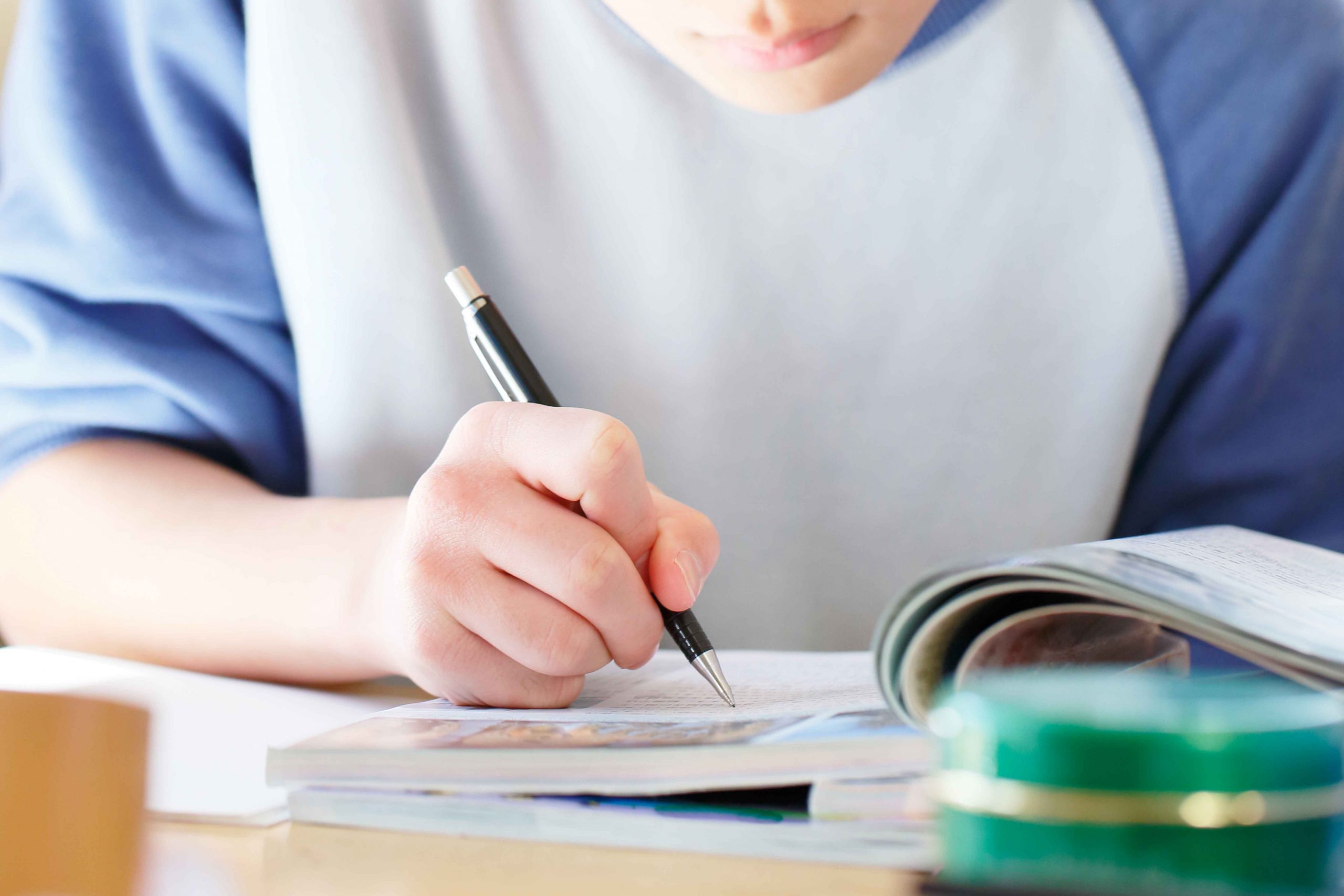

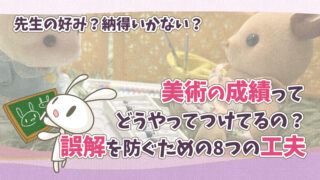


コメント