
こんにちは。
元美術教師のうさぎ先生です。
今回はわたしが美大生の時に教員採用試験対策として活用していた書籍をご紹介します。
- 先生になるためにはどんな勉強が必要なのかを知りたい
- 身近には教員志望者が少なく、教採に関する情報が欲しい
- 他の人がどんな本で教採対策をしているのかに興味がある
こんな方におすすめの記事です。
ちなみにわたしが実際に受験したのは2011年夏実施の大阪市と私学1校で、ありがたいことに新卒で両方の合格を頂戴することができました。
今とは試験内容が変わっている部分もあるかと思いますが、ぜひ最後までご覧くださいね。
教員採用試験対策の本を買った理由
教採仲間が少なかった美大生時代
大学や学部によっては身のまわりに教採仲間がたくさんいる大学もあるかと思いますが、わたしの出身大学では当時一学年に4、5人程度でした。
美大は一般的な大学と比べるとそもそも母数が少ないこともありますし、デザイン会社への就職や大学院進学などを選択する同期が多かったのです。

教育学部出身の方とは
まったく違う環境だと思います
ありがたいことに教育心理学担当の先生が定期的に勉強を見てくれていたのですが、なかなかそれだけでは足りなくて、個人的に勉強をする必要がありました。
今ほどはインターネットも発達していませんでしたし、なかなか情報が得られなくて、とにかく勉強をするしかなかったというのもあります。
実際に受験した教採は「大阪市」と「私立校」
わたしが受験したのは2012年度の大阪市公立学校教員採用選考テスト(中学校・美術)と、私学の女子校です。
私学の方は過去問がないので対策が難しかったのですが、ありがたいことに新卒で両方の合格を頂戴することができました。
どちらに勤務すべきかとすごく迷ったのですが、自分自身が私学の女子校で育ったということもあり、また合格をいただいた私学の芸術教育をとても大事にする校風が魅力的に移り、大阪市の教諭は辞退届を出して私学の常勤講師を選びました。
今回の記事では、そんなわたしが採用試験用に購入した問題集をピックアップしていきます。
一般・教職教養試験用の本
大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の教職・一般教養 (大阪府の教員採用試験「過去問」シリーズ)/協同出版
わたしが実際に使っていた『大阪府・大阪市・堺市2012年度版』には、2006〜2011年度の6回分の問題・解答・解説が掲載されていました。
教職・一般教養試験の過去問と予想問題のみで全298ページです。
教職・一般教養試験は全教科の志望者が受験することもあり、用語解説や学習指導要領の掲載はありませんでした。
A5版で持ち運びやすいし、内容がまとまっているため便利な本でした。
各都道府県市の選考方法に内容を合わせて分析・編集されているシリーズなので、ある程度受験する自治体が決まってからの購入をおすすめします。
教員採用試験対策 セサミノート 一般教養 /東京アカデミー
一般教養試験に向けては、オープンセサミシリーズも便利でした。
こちらは特に都道府県市を意識した作りにはなっていませんが、わたしは私立学校の受験も考えていたので、特定の都道府県市以外の情報や傾向も知っておくべきだと思い購入しました。
いわゆる過去問とは違って、全国の情報をもとに東京アカデミー独自の編集がなされています。
B5版で穴埋め形式の問題・解答・解説になっています。中高生の頃のテキストを思い出すようなスタイルで、全279ページでした。
全国対応の『セサミノート』+該当自治体の『過去問』という組み合わせが、使いやすいと思います。
同じシリーズの教職教養タイプもありました。
教職教養ランナー システムノート/一ツ橋書店
教職教養試験に向けては、わたしはランナーシリーズを使っていました。
オープンセサミと同じく特に都道府県市を意識した作りにはなっていませんが、わたしは私立学校の受験も考えていたので、特定の都道府県市以外の情報や傾向も知っておくべきだと思い購入しました。
サブノート方式になっていて、教育基本法や学校法はもちろんのこと、西洋教育史や教育心理、教育課程などあらゆる要素についてとてもていねいに触れられており、全383ページの大ボリュームでした。
自治体によって問題数や配点も大きく異なるので一概には言えませんが、誤解を恐れずに言うと…「ここまでの知識量は求められないのでは?」とさえ思ってしまうほどの情報量です。

大阪市は教職教養少なめなので
ここまでいらなかったかも…
網羅性の高い本で勉強したい人におすすめのテキストです。同じシリーズの一般教養タイプもあります。
専門教養試験用の本(美術科)
大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の美術科過去問 (大阪府の教員採用試験「過去問」シリーズ)/協同出版
上に出てきたものと同じシリーズで、こちらは専門教養試験(美術科)のために購入しました。
わたしが実際に使っていた『大阪府・大阪市・堺市2012年度版』には2003〜2011年度の9回分の問題・解答・解説が80ページ近くに渡って掲載されていました。
技術や鑑賞については中高共通問題として、学習指導要領や指導案については中学校・高等学校を分けて書かれています。
出題傾向や予想問題、演習問題に加えて用語解説集、さらに学習指導要領(中学校・高等学校)を含んで全294ページでした。
A5版で持ち運びやすく、内容がまとまっているため便利な本でした。
各都道府県市の選考方法に内容を合わせて分析・編集されているので、ある程度受験する自治体が決まってからの購入をおすすめします。
専門教養についてはこのテキストに加えて、自分自身が生徒だった当時に使っていた美術の教科書が案外役に立ちましたよ。
また、教採用の本だと図版が白黒だったり小さかったりするので、カラーで見るために美術史の本も併用していました。
美術史の本については着任してからも教材研究に使えるので、教採の時点で好みのものを買っておいても損はないと思いました。
関連中学生に美術史を教える前に読んだおすすめの本 〜美術史ざっくり入門書編
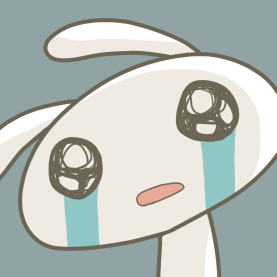
わたしは美大時代、
美術史が得意な方ではなかったので
鑑賞分野の勉強が結構大変でした…
おわりに
今回の記事では、わたしが教員採用試験対策で活用した本についてご紹介しました。
教育大だと大学独自のノウハウや教材、ゼミなどもありそうですし、大きく勝手が異なると思います。
もっと効率的な方法もあるかもしれません。
でも逆に言えば、教育大以外の方の中には、わたしと似た境遇で困っている方もいらっしゃるのかな?という気もするのです。
著作権の都合上、書籍の中身を載せてのご紹介はできないことが残念でしたが、これから教員採用試験を受験する方に少しでも参考にしていただけると嬉しいです。
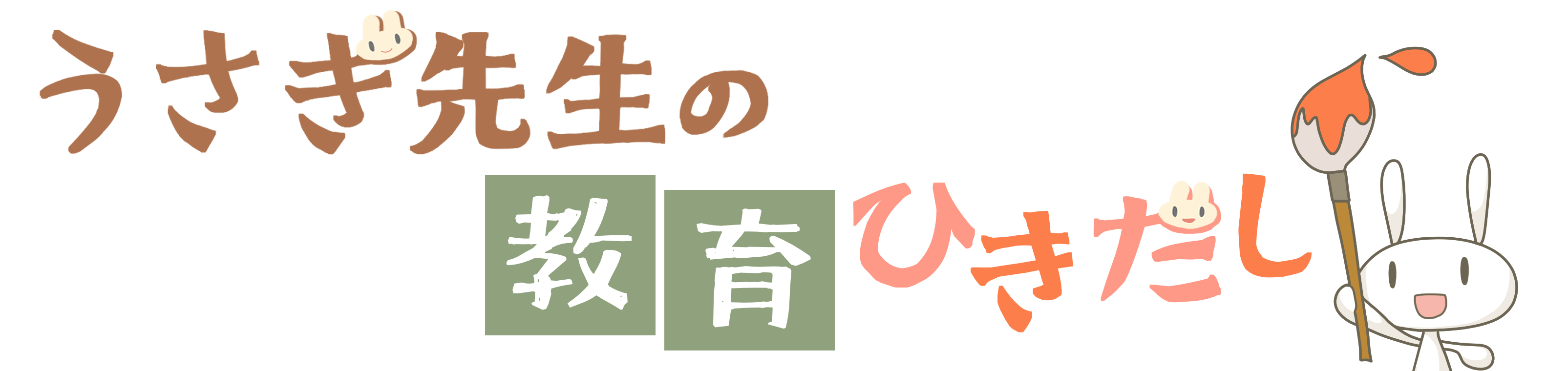
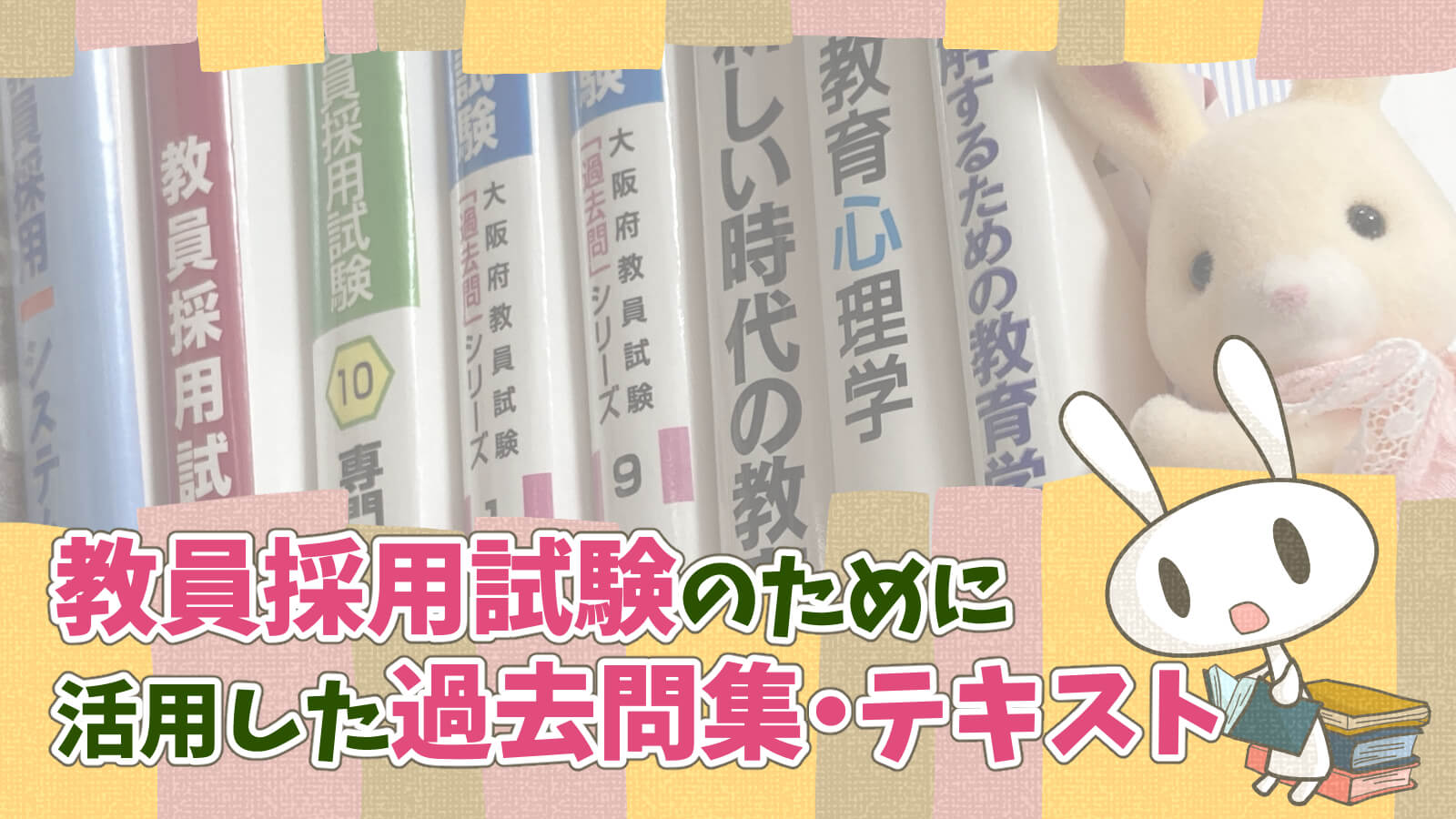
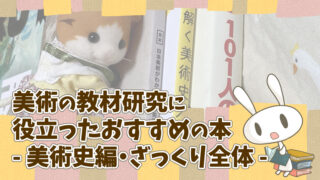
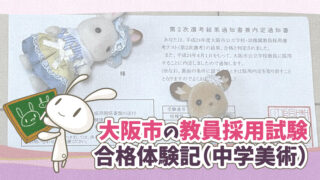


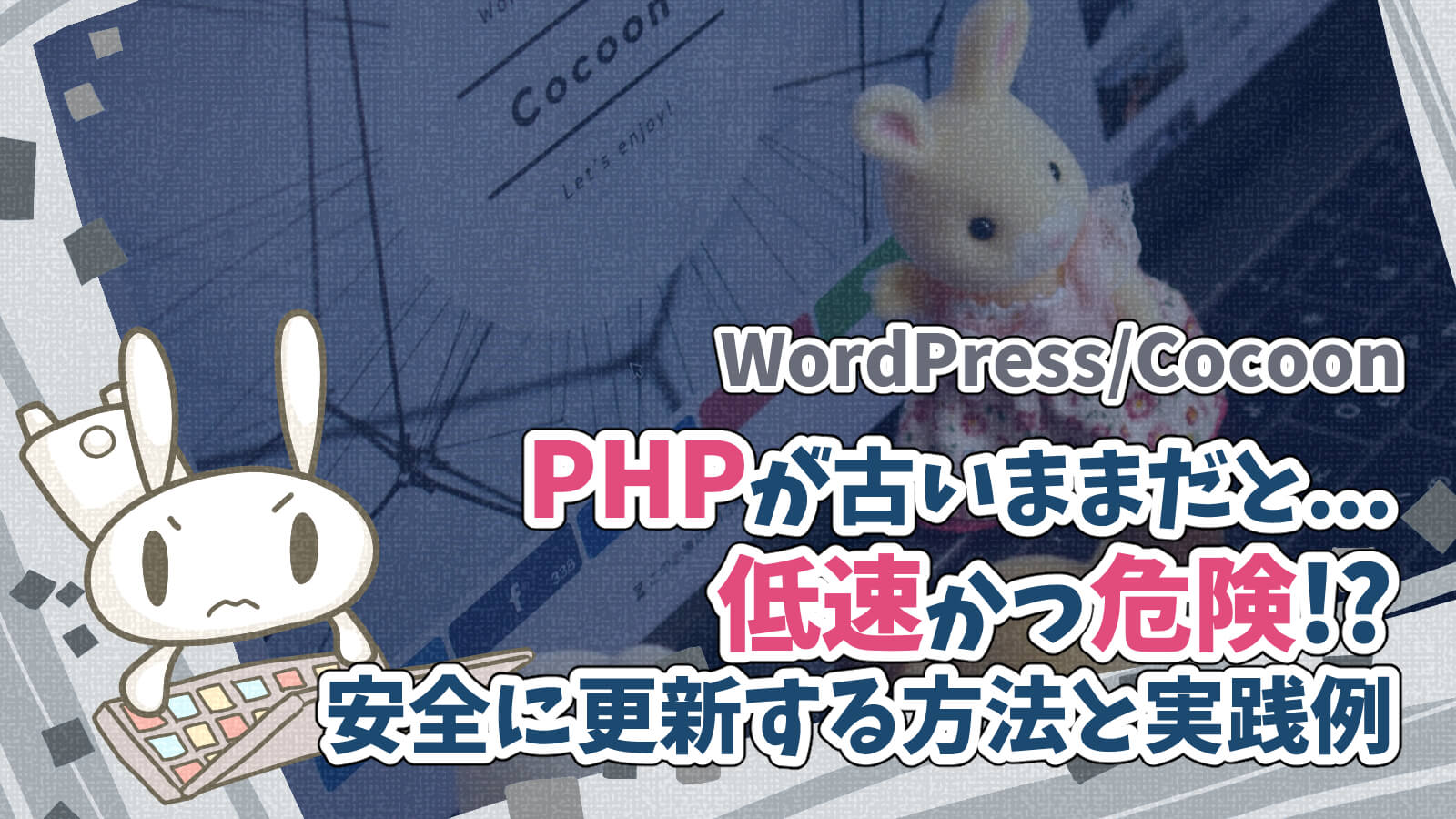

コメント